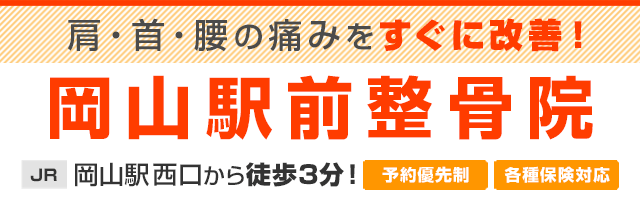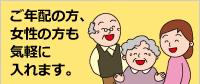巻き肩


こんなお悩みはありませんか?
①猫背で姿勢が丸くなる:巻き肩が強くなると、横から見た際に姿勢がかなり丸く見えてしまいます
②周りの人から内向的に見られる:巻き肩が強く丸い姿勢が常に続いている方は、周囲の方から内向的に思われることも少なくありません
③呼吸が浅くなる:肩が前方に内旋することで胸郭の拡張が制限され、呼吸が浅くなる場合があります
④頚肩こりが強くなる:巻き肩になると、肩周りや肩甲骨周りの筋肉が健常な方に比べて硬くなり、こりにつながります
⑤肩の可動域が狭くなる:巻き肩によって肩甲骨が外転し、硬くなった筋肉や上腕骨の動きを肩甲骨が制限するため、可動域が狭くなってしまいます
これらの症状にお悩みの方は、早めに対策を講じることが大切です。ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください
巻き肩について知っておくべきこと

上記でご紹介したお悩み以外にも、巻き肩によって引き起こされるトラブルは数多くあります。「この悩み、巻き肩が原因かもしれない」と感じられた際には、お早めにご相談ください。
巻き肩であっても、自覚がない方は多くいらっしゃいます。実際に肩の不調でご来院された方から「姿勢は良い方だと思っていたので、原因が分かりませんでした」とお話しいただくこともあります。
しかし、当院で姿勢のチェックを行うと、肩が本来の位置よりも前に出ていたり、背中が丸くなっていたりするケースが見受けられます。そういった方には、横から撮影した姿勢の写真を一緒に確認していただき、ご自身の状態を自覚していただくようにしています。
まずは、ご自身の症状がどこから来ているのかを知ることが、とても大切です。
症状の現れ方は?

巻き肩の方は、日常生活の中で巻き肩を誘発するような行動を無意識にとっていることが多くあります。たとえば、デスクワークやパソコン作業で長時間腕を前に出している方や、ご自宅でスマートフォンを長時間操作している方などに多く見られます。このように、同じ姿勢が長時間続く方は、特に注意が必要です。
一度、ご自身の普段の生活の中での姿勢を見直してみてください。
中には、親御さんからの遺伝によって巻き肩の傾向が見られる方もいらっしゃいます。若いころから肩こりに悩まれている方は、ご両親の姿勢を確認してみてください。もしかすると、遺伝が影響している可能性もあります。
このような姿勢不良を放置していると、肩こりや痛みなどの症状につながるおそれがあります。早めの対応が大切です。
その他の原因は?

巻き肩になるその他の原因として挙げられるのが、横向きで寝ることです。これもデスクワークなどと同様に、巻き肩を誘発する姿勢が長時間続いてしまうことが要因となります。寝ている間の姿勢は意識的に制御するのが難しいため、予防するのは容易ではありません。そのため、早めの施術が大切になります。
また、ストレッチ不足のまま筋力トレーニングを行う方は、巻き肩が強くなる傾向があります。たとえば、胸の筋肉(大胸筋など)のトレーニングを集中的に行い、ストレッチを怠ってしまうと、胸の筋肉が上腕骨を前方へと引っ張る力が強くなり、巻き肩を誘発しやすくなります。
さらに、前鋸筋の機能が低下すると、肩甲骨が外側に引っ張られやすくなり、これも巻き肩の要因となります。
巻き肩を放置するとどうなる?

巻き肩を放置していると、多くの場合、肩こりや痛みへと発展する可能性があります。
巻き肩になると、まず上腕骨の内旋が強まり、次に肩甲骨の外転および内旋が進行します。その結果、頸椎から肩甲骨上角に付着する「肩甲挙筋」や、脊柱の横突起から肩甲骨内縁に付着する「菱形筋」といった筋肉が、常に引き伸ばされた状態で緊張し、硬くなってしまうことがあります。
この状態が続くことで、可動域の低下や肩こり、痛みなどの症状が現れる可能性があります。さらに進行すると、硬くなった筋肉が神経を圧迫し、しびれや感覚の鈍化といった神経症状につながることもあります。
これらの症状の軽減には、早い段階での施術が重要です。悪化してしまう前に、早期の発見と施術を心がけていきましょう。
当院の施術方法について

当院では、巻き肩や巻き肩が原因で起こるさまざまな症状に対して、いくつかの施術をご用意しております。
まず初めに、指圧と遠赤外線を用いて、肩周りや肩甲骨周囲の筋肉の硬さを丁寧に緩めていきます。その後、多くの方には上半身の矯正施術を行い、症状の軽減が期待されます。この矯正施術により、可動域の向上や巻き肩の状態に変化が見られるケースも多くあります。当院では、この矯正施術を基本とした施術方針を取っております。
ただし、この施術だけでは症状の軽減が見られにくい場合には、肩甲骨はがしや上半身の筋膜ストレッチといった施術を追加で行うことがあります。
肩甲骨はがしは、肩甲骨周囲の筋肉が癒着して巻き肩を引き起こしている場合に行い、肩甲骨の外転の軽減が期待できます。
また、上半身の筋膜ストレッチは、胸筋や前鋸筋の柔軟性の低下が原因と考えられる場合に実施し、筋肉の柔軟性を高めることを目的としています。
軽減していく上でのポイント

巻き肩の症状を軽減していくうえで、いくつか重要なポイントがあります。まず挙げられるのが、施術の頻度です。
骨格のバランスを整える施術は、変化が現れやすい一方で、元の状態に戻りやすいという特徴があります。多くの方は、施術後おおよそ3日ほどで元の状態に戻りやすいため、骨格が戻り切る前に再度施術を行うことが理想とされています。そのため、週に2〜3回の施術が推奨されております。
また、デスクワークなどで同じ姿勢が長時間続いてしまう方は、施術を受けていてもなかなか変化が出にくいことがあります。そういった方には、お仕事中に1時間に1回、1分間だけでも意識して肩甲骨を脊柱に寄せ、胸を開くような姿勢をとることをおすすめしております。
このような簡単な姿勢の工夫を取り入れることで、筋肉の緊張がゆるみやすくなり、つらさの軽減が期待できます。
監修

岡山駅前整骨院 院長
資格:柔道整復師
出身地:鳥取県境港市
趣味・特技:水泳、バドミントン、掃除